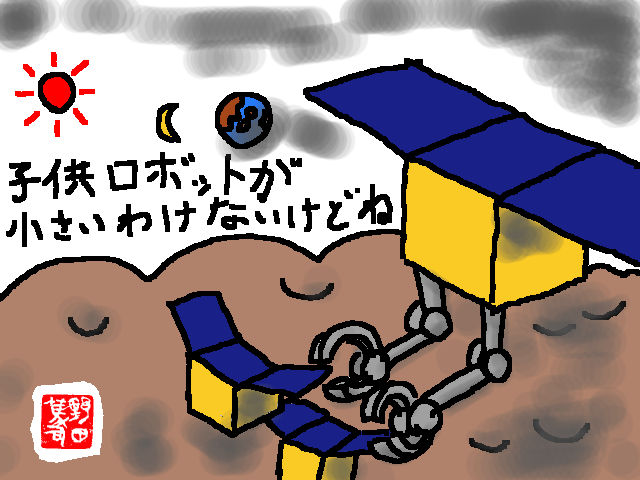惑星や小惑星への探査や開拓にロボットが有効であることは間違いない。無人探査は当然のこと、人間の居住を目的とした開拓であってもロボットの手助けが必要不可欠であることは、誰も異論が無いだろう。
ロボットには、以前から次の三項目が大きな課題としてあげられていた。
(1) 二足歩行
(2) 人工知能
(3) 自己増殖
御存知のように、二足歩行については10年ほど前に大きな進歩があり、そこでは日本の技術が先端を走っている。だが、未だに二足歩行が、真の意味で実用的に使われることは無く、アプリケーション応用が現在進行形の研究だと言える。
人工知能については「人工知能」と言う言葉自体が陳腐に思えるほど、ここ20年程度の間にエキスパートシステムやニューロコンピュータ、遺伝的アルゴリズムなど各種の方法論が提案され研究されているが、未だに「機械に心を持たせる」ことに決定的な解決の糸口すらつかめていない。
二足歩行と人工知能について書き続けていれば切りが無いが、本コンテンツの目的ではないので、この辺で打ち切り、本来の主題である自己増殖について語ろう。
自己増殖型ロボットとは、古くはフォン・ノイマンが提唱したいわゆる「フォン・ノイマン・マシン」を発端にしている。この「フォン・ノイマン・マシン」は、現在のコンピュータの基礎的な構造を示す「ノイマン型コンピュータ」の事ではない。月や火星等の惑星を、人が住めるように開拓するには、惑星改造用の機械・・この場合、「機械」にはロボットも含まれる・・を地球で建造して打上げ送り込むより、自分自身を複製する機能を持ったロボット・・自己増殖型ロボット・・を一台だけ送り込み、惑星上でロボットが2倍4倍と増え続けて、数が揃ったところで惑星改造した方が効率的だと言うものである。
もし、自己増殖型ロボットが実現可能であれば、月・火星開拓だけではなく、多種多様な分野で有効であることは明らかだ。私自身、自分のブログで発表しているように、小惑星に人類が広がることも自己増殖型ロボットがあれば、簡単に実現してしまうだろう。最初に自己増殖型ロボットを送れば、資源の豊かな小惑星で増えた後、無人で惑星間航行宇宙船を建造し、地球まで人類を迎えに来てもらえば良い。
しかし、もちろん残念なことに自己増殖ロボットは、二足歩行と人工知能よりも、ずっと実現が困難だと思われている。
だが、ここに来て、自己増殖ロボットの可能性に光明がさしてきた。それも、フォン・ノイマンが最初に提唱した惑星開拓、正確には「小惑星開拓」に、自己増殖ロボットの可能性が見えてきたのだ。
当然のことながら、多くの人に「条件が良い筈の地球上での自己増殖ロボットの実現の見通しが無いのに、小惑星での自己増殖ロボットが実現するとは思えない」と言う疑問が思い浮かぶだろう。そこで、自己増殖ロボット研究の可能性の前に、何故、地球上よりも先に小惑星での実用化が有り得るのかを説明しよう。
自己増殖型ロボットに対しては、技術的アプローチに大きく2つの方向性がある。一つは「マクロ的自己増殖型ロボット」であり、もう一つは「ミクロ的自己増殖型ロボット」だ。
マクロ的自己増殖型ロボットとは、ごく普通に私たちが思い浮かべるロボット程度の大きさの「機械」・・目に見え、手で持ち運べる大きさだったり、自動車程度の大きさだったりする・・であり、フォン・ノイマンの時代より、最初はマクロ的自己増殖型ロボットのアプローチが主流だった。だが、誰もが気がつくようにロボットの最も簡単な構成要素である構造体(骨格とか甲殻とか言った強度を支えるもの)ですら、自分自身で作る事などできそうもないのである。
十数年前から、マイクロ・マシン、ナノマシンと言ったミクロ的自己増殖型ロボットのアプローチが提唱され、盛んに研究された。マイクロ・マシン、ナノマシンは分子や原子レベルの工作を可能とする機械を基盤している。つまり、生物の細胞分裂そのものを模倣すると理解しても良い。しかし、ある程度具体的なマイクロ・マシンなどが実現してくると、その限界も見えてくる。ミクロ的なアプローチは、一時の熱が去ってしまうと、難しいことの実現を更に難しいことの実現に先送りしているだけだと言う理解だけになった。
なお、「マクロ的自己増殖型ロボット」の一部に「ミクロ的自己増殖型ロボット」を組み合わせるなどのバリエーションは数限りなく提唱されているが、ここでは、それらの紹介は省略する。
自己増殖型ロボットの研究が暗礁に乗り上がったとき、スタフォード大学の Shitsua Dano 博士が一昨年発表した論文:「限定的自己増殖型ロボット」の中で、「マクロ的自己増殖型ロボットによる小惑星開拓」の可能性が示唆された。博士によると「マクロ的自己増殖型ロボット」に絞ったのは、現状もしくは現状の技術の延長線上で実現可能なことを優先したためで、ロボットの活躍の舞台を小惑星にしたのは、次の (a) (b) が理由とのことである。
(a) 大きさ
ロボットが大きくなれば、構造部の材質に寸法の三乗とも四乗とも言われる強度が必要になる。例えば、直径1ミリの球体であれば、水の表面張力と言う極めて弱い力でも、形を保つことが可能だ。これは撥水性の高い物質、たとえば植物の葉の上の水滴を見ても明らかだ。だが、直径1センチの球体を水の表面張力だけで作るのは困難で、直径10センチとなると全くの不可能となる。
生命の基礎となる細胞が、極めて小さいのは、これと無関係ではない。細胞の大きさは、水や蛋白質、油などの表面張力や粘性抵抗、分子間力で構造が維持できる小ささなのである。この大きさを超えると、強度を保つ構造部材が別途必要になる。生物であれば、昆虫の甲殻、脊椎動物の骨などだ。
マクロ的自己増殖型ロボットの場合、プラスチックや金属の構造体が考えられる。だが、原油を精製してプラスチックを製造するプラントや、鉱石から金属を精錬する溶鉱炉を自己増殖型ロボットに入れ込むことは極めて複雑で大規模になり、とても簡単に実現することなど不可能であることは想像に難くない。
だが、ここで今一度考え直して欲しいのだが、そもそも構造強度が必要になる最も大きな要因は重力であると言うことだ。もし、重力が極めて小さいなら、プラスチックや金属等を用いる必要がなく、ずっと構造強度の弱い材質を使ってロボットを構成することが可能になる。例えば、スペースシャトルの内部のように無重量環境では、水の表面張力で、地球上では不可能な10センチの球でも形を保つことができる。
小惑星の重力は極めて小さく、例えば「イトカワ」の表面重力は地球の数十万分の1と言われ、このような重力下では、極めて弱い構造材を使うことが可能となる。Shitsua Dano 博士は、水の表面張力を使うのではなく、太陽から6億キロ以上離れた軌道で、水(正確には氷)を大量に持つD型小惑星の上で、太陽光をエネルギー源にして融かした氷を再び凍らせながら、構造体や機構部品を作る方法を提唱している。
(b) 他の『自己増殖ロボット』の妨害
地球上においは、人間が作った鈍間な自己増殖ロボットがモタモタと増殖作業を行っているうちに、数十億年間に進化したより優れた自己増殖ロボット・・つまり生物が妨害し、増殖を防ぐ。確かに、ロボットが増殖に必要な作業をしている間にカラスやネズミがつついたり、かじったりすることは想像に難くない。
博士の提唱する自己増殖ロボットは、活躍の場を小惑星に限ったが、それまで全く不可能と思われていた自己増殖の実現可能性を示すことで、各界に議論を呼び、停滞していた自己増殖ロボットの研究に活性化をもたらしたことは、既に旧聞に属する。
だが、ご存知のように Shitsua Dano 博士の提唱には、大きな欠点があった。博士の提唱には、構造体や機構部品の製造は含まれていたが、肝心の電子部品は触れられていない。太陽電池をエネルギー源にし、小型のコンピュータにより制御される自己増殖ロボットだが、太陽電池やコンピュータを作るためには、シリコン結晶を成長させ、その上に各種の電子回路を作りこむ「半導体工場」が必要である。現在の半導体工場は極めて大規模で複雑であり、とても自己増殖型ロボットの中に入るものではない。
博士も、それを十分に承知しており、妥協案として、コンピュータを構成させるマイクロプロセッサやメモリ、太陽電池セルと言った部品は、地球で生産し、ロケットを用いて小惑星に送り込まれる計画となっていた。全ての構成部品を自己増殖するわけではなく、限定的な部分のみを増殖させる、これが、「限定的自己増殖型ロボット」の「限定的」と言う言葉の意味するところである。
博士の論文は大きな反響を呼んだが、博士に対して否定的な意見も少なくなかった。太陽光輻射や放射線など、重力以外の自己増殖ロボットに対する外乱が過小評価されており、博士の見積もりは楽観的過ぎるとか、小惑星に対する自然破壊や汚染が問題だなどと反対意見は多いが、やはり最も多数を占める批判は、電子部品を地球からの補給に頼る『限定的』な部分に集中した。
そもそも、自己増殖ロボットは、指数関数的に数を増やすロボットの効果を期待するのが、電子部品を限定的にすることによって根本的に増加の足かせになっていると言うのが、反対意見の主旨である。博士は、地球より供給しする電子部品をごく少品種で軽量のものに限ることにより、大きな問題にはならないと反論しているが、説得力に乏しいことは否めない。
このように自己増殖ロボットの実現性の可否について先行きが見えない状態が続いていたが、つい先日、この議論を収束させるような発表があった。
MlT の Chii Uyu 博士と Lee Saa 博士が、小惑星を見立てた岩石成分を材料に自己増殖ロボットの試作モデルがシリコン結晶を成長させ半導体を実証実験に成功したと発表したのだ。彼女たち(名前から判るように、2人の博士は中国系アメリカ人女性だ)によると、試作モデルの製造できる半導体は、地上で一般的に使われている半導体より集積度でも消費電力でも 1000万倍も性能が悪い。つまり、マイクロプロセッサ黎明期の 8080A (トランジスター 6000個に相当)程度のLSIを作ると、最新の Core i7 (トランジスター 7億個に相当)の100倍以上の大きさと消費電力になると言う。実用化のためには、少なくとも100倍から1000倍の性能向上が必要と思われるが、彼女たちの弁を借りると「この技術は、まだ生まれたての赤ん坊で、ボーアの法則に沿って進歩していけば、実用となるのに、そんなに時間はかからない」との事だ。
もちろん、これが決定打となり、小惑星における自己増殖ロボットが可能になるとは限らない。半導体製造にわずかな可能性が見えてきただけで、他にも越えなければならないハードルは数多くある。だが、最も実現困難と思われた半導体製造だけに、これに可能性が見えてくると、にわかに自己増殖ロボットの実現に向けた議論が活気づいてきた。
先のスタフォード大学の Shitsua Dano 博士は、早くも新たな半導体製造プロセスを組み込んだ自己増殖ロボットの青写真を描き発表している。新たな自己増殖ロボットは1500kg (ハヤブサの3倍)の立方体をしたロボットで、博士によると「5年以内に基礎研究を終わらせ、更に5年で製造し、打上げる」と言う。
もし、本当に10年後に自己増殖ロボットが完成し、ロケットで打上げられ、数年毎に倍々に増えていくなら、半世紀後には100万台のロボットに増え、文字通り小惑星帯は、ロボットで埋め尽くされるだろう。100万台のロボットは、小惑星を改造し人が住める環境を作り、惑星間宇宙船を作って、人類が移り住む準備をすることもできるし、小惑星の資源や小惑星上で育てた食物を地球に送ることができるかもしれない。
この構想が本当に実現するのかは、今のところ、誰にも予想もつかないが、もし実現したら、世界が大きく変わってしまうことだけは間違いない。
注意
ブログのコンテンツの内、「告知」など時期よって情報価値が無くなるのは除いてある。また、コンテンツに付いたコメントは書き込み者に著作権があるものと判断し、ここに持ってきていないので、コメントを見るときは、元々のブログコンテンツを参照してもらいたい。
その他、ブログ発表後、コメントなどの内容を反映するなど、内容を変更しているものもあるので、注意してほしい。