
「Newton」と言う科学雑誌の1996年10月号に「宇宙旅行のテクノロジー」と特集記事が載っている。この記事の中に反物質ロケットとバザード・ラムジェットを使った恒星間宇宙船の紹介が、それぞれ見開き2ページずつ載ってた。実は、この記事の著作者は、実は紛れも無く私である。この記事は、僅か2ページで、「反物質ロケット」を紹介したため、中途半端な内容になり、私の中で消化不良を起こしたままとなっていた。今回、反物質ロケットについて、詳細な検討結果を研究報告として、発表することにした。
「Newton」の記事を書く時、裏付けの為の計算などをまとめた資料を作った。その資料は、1年半以上に渡って、お蔵(バックアップ用のMOディスクのこと)入りしていたが、この度、加筆訂正を加えて、本報告書とした。なお、最初、小型無人恒星間探査機だった計画が、「Newton」編集との打合わせを減る度に大型化し、有人恒星間宇宙船に膨れ上がったことを覚えている。今、手元に「Newton」を持っていないので、果たして、この資料通りの設定だったのか、さらに大型化して記事にしたのかは良く覚えていない。
反物質やそれを応用した宇宙機システムについては、現在の技術で、簡単に実用化できるような物ではない。しかし、反物質は、科学的には存在が確認され、その特性から、宇宙開発においての応用が期待される。
なお、断っておくが、この反物質ロケットのような実用の見込みが極めて少ない研究は、個人の趣味として行なっているだけで、国民の税金を使った業務として行なった訳ではない。あくまで個人的に、同好の志達が勤務時間外に集まり、語らっている中で生まれた内容である。
本研究報告の内容を以下に示す。
反物質ロケットのアイデアは、意外と古く、ゼンガー博士により1930年代には提案されており、この場合、むしろ「光子ロケット」と言う名称の方が有名である。反物質ロケットを初め、核融合ロケット、光子ロケット、バザード・ラムジェット等の未来的な宇宙推進システムについては、石原藤雄氏の「銀河旅行
part I & II」(ブルーバックス絶版)やロバート・L・フォワード著の「SFはどこまで実現するか」(講談社ISBN4-06-132801)に詳しく紹介されている。
本研究の目的は、反物質を応用した宇宙機システムであり、反物質の理論的な詳細説明では無い。研究内容の第1項と第2項については、簡単に反物質の紹介と製造方法を紹介するに留める。正直に白状してしまえば、私自身が理論物理学の専門家でも無いので、第1項と第2項については、前述の参考文献の受け売りに過ぎない。
本来の目的の内容の第3項及び第4項であり、この辺は私のオリジナルである。付録に添付した計算式の導出も私自身が行なったので、もしかしたら根本的な計算間違いをしているかもしれない。「最良質量比は約4.92」の当たりは気に入っているが、簡単に導出できるので誰かが先に論文発表してしまっていると思う。面倒なので、文献のサーベイすらしていない。万一、私が最初だったら、こんなWebページにするより、宇科連かISTSに出すべきなんだろうけどね。もっとも、こんな海の物とも山の物とも判らん反物質ロケットの論文なんて、宇科連もISTSも受けとってくれないかもしれないけど。
(そう言えば、そろそろ今度のISTSの論文を書かなきゃならんぞ。どうせ、私は出られないから、N君かKさんが代理発表するんだろうけど。まあ、大宮より鵜飼いの方が面白かったから良いけど。)
自然界に存在する物質はほとんど全てが正物質であり、陽子、中性子、電子で構成される。図1のように、各正物質に対応して、反陽子、反中性子、陽電子が存在し、これらを反物質と呼ぶ。

反物質は電荷が正負逆転する以外は、質量も万有引力も運動量等の物理的特性は正物質と全く同じであり、正物質と同様の運動を行う。反物質は、よく誤解される様な「反重力物質」ではない。
反物質は、量子力学の理論から存在が推測され、陽電子は1932年、反陽子は1955年にそれぞれ発見されている。反重力物質やタキオン粒子のように存在が「希望」されている物質や、重力波やブラックホールのように理論上存在が確実視されていても、確認されていないものとは異なり、反物質は存在が確認されている物質である。
反物質は、存在が確認されているだけではなく、生成方法も確立している。日本の場合、反物質「製造プラント」は、「高エネルギー研究所」にある。高エネルギー研究所には、電子の反物質である「陽電子」を生成し、これを大型粒子加速器「トリスタン」で、電子と衝突させる研究を行っている。
陽電子よりも遥かに大きな反陽子の「製造プラント」はスイスのCERN等にあり、ここでは、反陽子と陽子を粒子加速器の中で衝突させる研究を行っている。
反物質の物理的な性質は、ほとんど全てが正物質の性質と変わらない。反陽子と陽子、反中性子と中性子、そして、陽電子と電子は質量が等しい。そして、Newtonの万有引力に乗っ取った引力を発生し、互いに引き合う。(反発しあうわけではない。)
また、力に対する加速や運動量・エネルギー保存則にも従う。反陽子と陽子、陽電子と電子の持つ電荷は、正負が反転しているが、持っている電荷の物理的性質はマックスウェルの法則に従う。
唯一、反物質が正物質と異なる性質は、正物質とぶつかると同質量の正物質と反物質が反応し、(
は反応した正物質と反物質の合計質量)のエネルギーが放出される。これを対消滅と呼ぶ。対消滅の発生エネルギーは、質量に等しいため、単位質量当たりのエネルギー(エネルギー密度)は、理論上最大になる。
従来のロケットに使われる化学反応のエネルギー密度に対し、核分裂は約100万倍、核融合は、数千万倍であるが、対消滅のエネルギー密度は約100億倍にもなる。このエネルギー密度の高さが、従来の常識を越える宇宙機への応用が期待させる。
反物質は、自然界にはほとんど存在せず、人工的にエネルギーから製造することが、現在のところ、唯一の獲得方法である。つまり、反物質はエネルギー資源に成り得るものではなく、核分裂・核融合等と同列に扱うべきものではない。むしろ、これらの既存のエネルギー源から、充電する蓄電池と考えた方が良い。
この反物質蓄電池の特徴は、
ことである。
当然、これ程、充放電効率の悪い蓄電池が役に立つのかと言う疑問が生まれる。しかしながら、一般的な地上での使用はともかく、宇宙での利用は、質量効率の良さが充放電効率の悪さを補って余りあるのだ。
真空中のエネルギー密度を高めると、質量/エネルギー変換のの逆変換で物質が生成される。この時、正物質と反物質は共に1/2の確率で、同数出現する。
このように真空中でのエネルギー密度が高まり、正/反物質が生成されることは、自然界ではビックバンの時にあった。ビックバンの時、同数出現したはずの正/反物質は再び反応しエネルギーとなったが、最終的に正物質が残った。(なんで、同数出現したはずの正/反物質の内、正物質だけが残り、現在に至っているのか、私に聞かないで!)
反物質は、仮に生成されても、すぐに正物質と反応して消えてしまうので、自然界から大量に得ることは不可能である。しかし、人工的に造りだすことは可能だ。すなわち、無理矢理、真空中のエネルギーを高めてやる。
反物質、特に反陽子を得るためには、真空のチューブの中で、電磁波を使って、陽子を加速する。真空のチューブはリング状になっており、チューブの回りを磁気コイルが巻いている。磁気コイルの発生する磁界で陽子は曲がり、リング状に回転する。リングの中の陽子を磁力で加速をし続けることで、陽子の速度は果てしなく光速に近づいていく。これが粒子加速器である。粒子加速器は、スイスのCERN等にある。
陽子を光速の99%以上に加速すると、陽子の持つ運動エネルギーは、陽子の質量のエネルギーの100倍くらいになる。これをタングステンにぶつけると、陽子は蒸発し、真空中のエネルギーが高まる。この結果、正/反物質が生成される。ほおっておくと、反物質は正物質と反応して再びエネルギーとなり消えてしまう。生成した反物質である反陽子が、正物質と反応する前に磁力で取り出すことによって、反物質を得る。この時、現在の技術では生成した反陽子の内、1000個に1個程度しか、取り出すことはできない。
取り出した反陽子は、高温で運動量を持っており、高速で動いている。最初に粒子加速した真空チューブとは別の小型の真空チューブでやや温度を下げた後、再び最初の大型の粒子加速器で今度は反対に減速して速度を下げる。最終的には、もっと小さい真空チューブで、温度を下げたまま、保管する。ここまでの技術は確立しており、実際にCERNで行われている・・・らしい。この方法で1兆個、つまり1兆分の1グラムの反物質の貯蔵に成功している・・・らしい。
このままでは、反陽子はプラズマ状態なので大量には保存できない。別に造った陽電子(陽電子は高エネルギー研究所でも造ることができる)と合わせて、反水素にする。反水素にレーザを当てることで更に冷却し、磁気で封じ込める。反陽子・陽電子は安定した物質なので、漏れさえ無ければ理論的には半永久的に貯蔵可能である。
反物質の製造において、最大の問題は、とてつもなく効率が悪いと言うことだ。現時点では、1mgの反物質を得るためには1,000億ドルものコストがかかる。ロバート・L・フォワードは、反物質製造専用の粒子加速器を開発すれば、1mgのコストを1,000万ドル迄下げることが可能との見解を示している。
ロケットの原理を使った推進システムでは、燃料のエネルギー密度が、そのシステムの出せる最大比推力に関係する。
燃料のエネルギー密度をとするとき、最大噴射速度
と比推力
は次の様になる。なお、この式に、化学燃料のおおよそのエネルギー密度である
を代入すると、比推力は、432秒となる。
推進システムのエネルギー源に反物質とそれに同質量の正物質の対消滅を用いた場合、になり、最大噴射速度は光速になる。
実は、反物質を使った推進システムの最大噴射速度が光速になり、比推力が物理理論上最大になる。このことから、究極の推進システムとして「光子ロケット」のアイデアが生まれた。これは、単純に「比推力は高ければ高い程良い」という考えから、「最も噴射速度の速いすなわち比推力の高い光子を用いれば、最も良いロケットが作れる」というものである。しかし、現実的には「比推力は、高いほど良い」訳ではなく、仮に反物質が実用的になっても、光子ロケットは、かなり荒唐無稽なアイデアである。
一般的には、「噴射速度が速いすなわち比推力が高い程、良いロケットである。」と思われている。が、これは大きな誤りである。
地球から軌道に乗るのに必要な増速量であるを達成するために必要な質量比を、比推力との関係を図2に、比推力と総エネルギー量の関係を図3に示す。

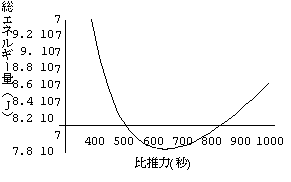
図2から、比推力が高い程、質量比が低くなる事が判る。しかし、比推力と総エネルギー関係は、単純ではない。図3から、総エネルギーは、比推力が650秒位で最も小さいことが判る。化学ロケットでは、比推力の最大がせいぜい480秒であるため、単純に「比推力が高い」ほど質量比も「総エネルギー量」も最小になる「良いロケット」と言うことができた。
しかし、反物質推進の場合、650秒よりも遥かに高い値が出せる。総エネルギー量は、そのまま、搭載する反物質の量に比例するため、製造コストの高い反物質を最小にする「総エネルギー最小」の比推力こそが、「最適なロケット」になる。
図4と図5に増速量の時の比推力と質量比・総エネルギー量の関係を示す。この増速量は、地上から、低軌道に投入し、空力減速を用いずに垂直に地上に戻るために必要な量である。また、木星の軌道に投入するために必要な増速量も
である。


図2から5を比べて判るように、要求される増速量によって、最適な比推力は変化する。
増速量及び
に必要な質量比と総エネルギー量の関係を図6、7に示す。


図6と図7から、総エネルギー量を最小にする質量比は約5のまま、変化しないことが判る。実は、総エネルギー最小化の質量比は、光速の30%程度まで、約4.92のまま、変化しない。すなわち、反物質推進システムでは、常に質量比5を目標に、噴射速度及び比推力を調整することによって、使用する反物質の量を最少にする。
なお、ここまでの計算では、問題の簡略化のために、推進システムがエネルギーを100%の効率で噴射することが可能と仮定している。また、加速の開始から終了まで、常に同じ噴射速度、すなわち常に同じ比推力にすることと仮定している。
エネルギー効率を下げることなく、使用する反物質を最小化するために、噴射速度すなわち、比推力を調整するためには、反物質を同量の正物質と反応させるのではなく、過剰の正物質と反応させ、余った正物質を噴射すればよい。
図8に、増速量を達成し、質量比を4.92として反物質の量を最小化する推進システムの一例の概念図を示す。

ここでは、反物質を使った宇宙機システムの例を2つ紹介する。
反物質推進を身近な低軌道や月旅行・惑星間飛行に応用した個人用の一人乗り宇宙船「パーソナル・ロケット」の例を示す。増速量が光速の30%程度まで、「反物質の質量を最小にする」最適質量比は4.92でる。つまり、パーソナル・ロケット乾燥質量1kg当たり、3.9kgの「水」が必要である。
例えば、乾燥質量1tの「パーソナル・ロケット」を考える。この場合、1トンの中には、構造体・タンク・エンジン等と人間1人と生命維持装置が必要である。このロケットのプロペラントとして、4トンの水が必要になり、20km/sの増速量を得るためには、反物質が1.7mg必要である。質量比5は、個人用のロケットとしては、少し大きすぎるかもしれない。図9に20km/sを得るための質量比と反物質の量を示す。

質量比が2では、反物質は2.3mg必要である。この程度の質量比なら、特殊な材料や構造は必要無い。構造体は「鉄」で充分である。これを反映した夢のパーソナル・ロケットのシステム構成を図10に示す。

このパーソナル・ロケットは、普通乗用車程度の大きさで、居住性は最悪であるものの、ちょっとした駐車場程度から離陸し、低軌道を回った後、垂直に地上に降りてくることができる。それも、空力的減速を一切使わずに!!
また、空力的減速を用いれば、月への往復も可能である。1tが丸々月に軟着陸することができる。さらに、片道とはいえ、木星への飛行も可能である。
反物質のコストを1mg当たり1,000万ドルとすると、2.3mgのコストは2,300万ドル・日本円にして23億円である。そう、従来のロケットよりも低コストだ。(もっとも、このコスト、前述のように現在の1万分の1と言う前提の元にあるが。)
但し、エンジン効率が100%とするのは余りにも非現実的であり、仮に効率を50%とした場合、反物質の必要量は2倍に増える。
反物質のコストが更にもう2桁程下がれば、本当に自宅の車庫からパーソナル・ロケットを飛ばすことは夢でなくなる。冬のボーナスを頭金にして、パーソナル・ロケットを買うことも案外近い将来の話しかもしれない。
最も近い恒星であるαケンタウリまで、4.3光年離れている。乗組員が生きている間にαケンタウリまで往復する反物質推進を使った恒星間探査船を図11に示す。

目的の星系に着いたとき、フライバイではなく、周回・着陸するためには、加速と減速が必要になる。このため、探査船の巡航速度は、増速量の半分になる。つまり、巡航速度が光速の20%の場合、増速量は光速の40%が必要となる。更に、目的の星系で、帰りのプロペラントや反物質を調達せず、あらかじめ持っていく場合には、巡航速度は増速量の1/4になり、巡航速度を同じく光速の20%とするときには、増速量は光速の80%が必要となる。増速量が光速の80%という値は、いかに反物質推進と言えども実現困難な値であり、ここでは、帰りのプロペラントは目的の星系で調達するものとして、検討する。
巡航速度が光速の20%の時、片道に必要な反物質の量は、最終質量の7%となる。αケンタウリまで、片道21.5年、往復43年+目的星系での探査期間と一つの船の中で、乗員は過ごさなければならない。乗員の人数を10人(男5人、女5人)とし、最終質量を100tと仮定する。プロペラント(水または水素)が、約400t、反物質が7t必要となる。但し、エンジン効率を50%とし、反物質の必要量を14tとする。
14tの反物質の持つエネルギーは、である。一般的な原子力発電所一基の1GWの発電器で、反物質への変換効率を0.05%(これでも、現状の何万倍も良い)とすると、14の反物質を得るには、1億6千万年かかる。逆に10年間で14tの反物質を得るためには、
の発電設備は必要となる。
帰りのために、目標星系で14tの反物質を得ることは不可能であり、図11では往復合せて28tの反物質を予め持っていくことにしている。
図12に全体シーケンスを示す。

なお、10年間で28tの反物質を得るため必要なの電力を太陽発電で行うことを計算した所、ほぼ、地球の直径に匹敵する太陽電池が必要なことが判った。また、反物質1mg当たり1,000万ドルとすると、28tの反物質は
ドル、日本円にして
円のコストがかかる。
反物質の紹介と、それを利用した推進システム及び宇宙機システムを紹介した。
反物質の最大の問題は製造コストである。これを桁違いに下げるのは、技術的なブレークスルーよりも、経済的なパラダイムシフトの方が可能性が高い。パーソナル・ロケットを起爆剤として、宇宙開発と反物質利用が大衆化し、大量生産・大量消費からコストダウンが飛躍的に起こることは期待できるのではないか。分の1〜
分の1のコストダウンも、コンピュータ業界における処理速度やbit当たりのコストを考えた場合、あながち不可能な話しではない。
パーソナル・ロケットによる大衆化と先端的な恒星間探査機を反物質が支える宇宙開発・・これが、今後のキーワードになるのではないだろうか。
エネルギー密度を及び
とするとき、最適噴射速度
と比推力
は次の様になる。(
は光速、
は重力加速度である。)
最終状態の質量を、プロペラントを
とするとき、質量比は
であり、増速量
は次のようになる。
従って、

となる。更に、
であり、最終状態の質量1kg当たりの総エネルギーは、
となる。この時、必要となる反物質の質量は次の式である。
及び
が最小になる質量比は、
をNewton法によって求めている。
なお、速度の遅いNewton力学領域では、総エネルギー量を最小化する質量比は
を満たすをNewton法で求めるとよい。これが、約4.92の値になる。